
「真実の自分」で顧客の心を動かす営業の極意|プルデンシャル生命保険株式会社 エグゼクティブライフプランナー 香川 壽宗さん
多様な業界を経験し、波乱万丈の道を歩んできたプルデンシャル生命保険の香川壽宗氏。
幾度もの挫折を経て見出した「真実の自分」で顧客と向き合う営業哲学が、多くの経営者の共感を呼んでいます。「6割できればいい」という若手育成の考え方や、潜在ニーズを引き出す技術、さらには世代間の「通訳者」としての役割—。
「人は商品ではなく人から買う」という本質を体現する香川氏の知見は、あなたのビジネスに新たな視点をもたらすことでしょう。ぜひ、本インタビューを最後までご覧ください。
様々な業界での経験―波乱万丈のキャリア

この度はインタビューをお引き受けいただき、誠にありがとうございます。香川さんの魅力に迫っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずは香川さんのこれまでのキャリアについてお聞かせいただけますでしょうか。

ありがとうございます。実は私のキャリアは波乱万丈そのものでした。大学時代には特定の就職先よりも、まずは生活費を稼ぐことが優先事項でした。当時は親との関係も少し距離があり、自分なりの自由な生活を送るために、コンビニの夜勤からスタートして、徐々に別のアルバイトをするようになりました。大学を卒業した後も、一般的な就職ではなく、生活のために始めた仕事を続けていました。

そこからどのようにして不動産業界に入られたのでしょうか?

接客業を約2年半経験した後、一度消費者金融の会社に就職しましたが、わずか1日で退職することになりました。その後、約3ヶ月ほど無職の期間がありました。「そろそろ就職しなければ・・・」という思いから、以前の知人のつながりで不動産賃貸会社に入社したんです。大学を卒業したにもかかわらず、当時は「とりあえず就職するか」という感覚で就職したように思います。

その後も様々な経験をされていますよね。

不動産賃貸会社で約3年働いた後、離婚がきかっけで退職することとなりました。その後、約1年半ほど社会から距離を置く時期がありました。

それは大変でしたね…。

そうですね。この時は本当に厳しい時期でした。しかし「社会復帰しなければ」という思いと、取得していた宅建(宅地建物取引士)の資格を活かして、土地開発の仕事に就くことにしました。親族のつながりを通じて再び不動産業界に戻り、その後もキャリアを模索する中でいくつかの職場を経験しました。そうした時期を過ごしているうちに、リーマン・ショックが訪れました。

それでプルデンシャル生命に入社されたんですね。

そうなんです。当時の年収は300万円にも満たず、埼玉の郊外でチラシ配布や飛び込み営業をしていました。将来を模索していた時に、ある飲み会で偶然プルデンシャルの方と知り合いました。その方が営業所長を紹介してくださり、結果的に入社する流れになりました。正直なところ、プルデンシャルという会社についての知識も、保険販売という仕事についての理解も十分ではありませんでしたが、「前職より待遇が良ければ」という考えで入社したのが、現在の私のキャリアの始まりでした。

ただ、現在ではプルデンシャル生命は香川さんのキャリアの中で最も長く勤務されている会社となっていますね。
何か特別な転機があったのでしょうか?

入社から最初の半年間は、目立った成果を上げることができませんでした。新たなお客様への展開ができず、紹介もいただけない状況が続きました。なぜうまくいかないのか、当時は原因がつかめませんでしたが、振り返ってみると不動産業界時代に身につけた強引な営業スタイルが原因だとわかったんです。

それはご苦労されましたね。どのように克服されたのでしょうか?

プルデンシャルにはセールスプロセスに関するマニュアルがあります。入社時に全員に配布されるのですが、当初は自分なりのやり方を優先していました。しかし結果が出ない状況に直面し、このマニュアルに立ち返ったところ、自分が思い描いていた営業手法とは全く異なるアプローチ方法がそこには記されていました。その後は毎日ロールプレイングを実践し、先輩方に指導をお願いするなど、「本気でやらないと生き残れないな…」と痛感しました。

成功者に共通する特徴として、「腹をくくる」ことが重要だと言われていますよね。
波乱万丈な経験をした人が成功する背景には、一度挫折を経験することで「本気で取り組もう」という強い決意ができるからなのだと思います。

まさにその通りですね。私の場合、1年半ほど社会から距離を置いていた時期は精神的にかなり厳しい状況でした。それと比べると「あのときよりはつらくないよね(笑)」と考えられるようになりました。お客様に断られることも、自分の営業スタイルを変えることも恐れなくなりましたね。

困難を乗り越えられた経験があるからこそ、現在の成功につながっているのですね。
そのストーリーは非常に心に響きます。

実は私自身、10歳の時に父を亡くしました。しかし父は生命保険に加入していたため、家族は5,000万円の保険金を受け取ることができました。当時、私は10歳、妹は6歳でしたが、経済的には何とか安定した生活を送ることができました。私立高校に進学することもでき、不動産も引き継ぐことができました。当初はこの経験と現在の仕事を結びつけて考えていませんでしたが、プルデンシャルでの仕事に苦戦していた時期に「父が残してくれた生命保険の恩恵を、一人でも多くの方に伝えていこう」と自分の仕事に対して意味付けをすることができました。そこからセールスに対する姿勢が根本から変わりました。

「6割できればいい」―マイスターとしての若手育成法

続いては、香川さんの後輩育成についてのお話をうかがえればと思っております。
プルデンシャル生命では、「マイスター制度」というものがあるとおうかがいしました。具体的にはどのような制度なのでしょうか。

マイスター制度とは、一定の役職に就いた者が約3人の後輩を担当し、育成する制度のことです。この制度では、担当する後輩の成長度合いによって、指導者自身も評価されるという仕組みになっています。

マイスターというと、職人の世界みたいでかっこいいですね!
実際にどのように指導されているのでしょうか。

始めた当初は、メンバーに自分と同じことができると思って指導していました。しかし、それは実際には難しいことだとわかり、「自分と同じコピーは作れない」という現実に当時はかなり葛藤を感じていました。『なぜこのメンバーは、私ができることができないのか』と思っていた時期が長い間ありました。その事実を認めるまでに少し時間がかかりましたが、今ではシンプルに『6割できれば十分だ』と考えられるようになりましたね。

「6割できればいい」という考え方は非常に現実的ですね。
完璧を求める方も多い中で、そういう視点は新鮮です。

そうですね。完璧を求めないという姿勢が大切だと思っています。良くも悪くも過度な期待をしないという考え方ができるようになってから、周囲からも認められるようになりました。後輩たちも徐々にできることが増えていきましたね。こうした経験を通して、自分の能力の6割程度を発揮できる人材が多く在籍している組織の方が、結果的には効率よく機能するということを実感しました。

なるほど。その『6割理論』を実践されてみて、後輩の方々の成長はいかがでしょうか?

マイスター制度を3年間で卒業するという期限を設けており、その期間内に保険業界の優績者に与えられる称号であるMDRT(Million Dollar Round Table)の基準達成を目指して共に努力しています。現在のメンバーでのマイスター制度が始まってちょうど1年が経過したところですが、メンバー全員が様々な気づきを得て、成長していると感じています。
MDRTとは
1927年に発足したMillion Dollar Round Table(MDRT)は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。

実際にどのようにメンバーと関わっておられるのでしょうか?
具体的な取り組みについてお聞かせいただけると幸いです。

私自身は構想を描いたり想像を膨らませたりするのが得意なので、後輩一人ひとりと対話し、各メンバーに適したアプローチを提案するようにしています。「もし私であれば、このようなアプローチを取るかもね」という形で自分の考えを押し付けないコミュニケーションをしながら、そのメンバーが持っている得意分野を見出して発揮できるようにしてあげると、メンバーの成長スピードが大幅に加速していきました。

それぞれの個性を尊重する姿勢が素晴らしいですね。
自分と同じ手法を押し付けるのではなく、一人ひとりに合わせた指導をされているのですね。
香川さんのアドバイスの結果、実際にメンバーのみなさんはどのように行動されているのでしょうか。

みんなそれぞれ強みを活かして活動しています。例えば、あるメンバーは茨城マーケットに特化すると決め、マーケティング活動を行った結果、大きな成果をあげることができました。今年は社内コンテストで最高記録で入賞しそうです。一方、他のメンバーは、オンラインでの活動に特化して取り組んでいます。オンライン商談だけでコンテストに入賞するという目標を立てて頑張っています。このようにして、それぞれのメンバーの得意分野や興味を活かすような指導をしています。

それは素晴らしい取り組みですね。
香川さんは、マイスター制度以外にもメンバーの活躍をサポートする活動をされていると伺いました。
そちらのチームにおいても同様の関わり方をなさっているのでしょうか。

そうですね。同様の関わり方をしています。実はそのチームは、マイスター制度のチームよりもさらに大規模なものです。私自身が不動産に強い関心を持っていたこともあり、住宅メーカーとタイアップして、家を購入する際のライフプランニングをサポートするチームを立ち上げました。これが現在では40~50人規模のチームに成長し、様々な企業と連携しながらお客様のご紹介をいただいています。

40~50人ものチームを率いていらっしゃるんですね!
そのチーム作りにも「6割理論」が活かされているんでしょうか?

そうですね。チームのマネジメントは、当初は私が全てやってしまっていました。しかしチームの規模が大きくなるにつれて、徐々にマネジメントを任せる人材を育成し、その人にメンバーの指導を任せるという体制が必要になってきたんです。問題が発生した際には、適宜サポートに入るという形で、全ての業務を自分で抱え込まない方向へと転換していきました。この移行期間はとても大変でした(笑)

チームの規模が大きくなると、任せることの重要性が増しますよね!
チーム運営をより円滑にするために、他に取り組まれていたことなどはありますか。

業務内容のマニュアル化は実施しました。まずはマニュアルを確認してもらった上で実践してもらいます。その後、マニュアルの中で理解しづらい部分や実践で行き詰まっている箇所があれば、その部分を重点的にサポートするようにしています。このようなことを続けていると、メンバーの成績も徐々に向上するようになります。

そのような地盤固めはとても重要ですよね。
ちなみに、「リーダーとしての責任の取り方」についても香川さんにはポリシーがあると伺いました。
具体的に聞かせていただいてもよいでしょうか。

メンバーは一生懸命努力しているのですが、それでも提携している不動産会社から厳しいお言葉をいただくことがあります。それらすべてをリーダーである私が受け止めるという覚悟を持って取り組んでいます。実際にそのような状況が発生した際には、まず事実関係を確認し、メンバーと一緒に謝罪に伺います。リーダーがこのような対応ができるかどうかは、先方との信頼関係はもちろんのこと、チームのクオリティを大きく左右すると思っています。

「香川さんのリーダーとしての『覚悟』を感じさせていただきました。
ちなみに、40~50人のチームを構築される中で、特に意識されていることはありますでしょうか?

自分が好きだったことを、みんなと共有して活性化させるということですね。私は元々不動産業界にいたので、不動産が本当に好きでした。プルデンシャルに入社してからも、不動産業界での経験を活用しながら保険の仕事に活かせないかと思っていました。そこで、住宅メーカーとタイアップして、家を購入する際にライフプランニングのサポートをするという方法を考えました。

自分の情熱をチームの強みに変えていったわけですね。
やはり、自分の長所を最大限に活かしていくことがいかに大切かを教えていただきました。
ありがとうございます。

若手を育て、営業組織を強くしてきた
経営者の想いを発信しませんか?
100名以上のCEOインタビューを掲載してきたコントリが運営するセールスカレッジでは、営業組織を育て、チームで成果を出してきた経営者の取り組みや想いを、多くの読者にお届けしています。あなたの育成ノウハウが、同じ課題を抱える経営者の道標になります。
「真実の自分」で顧客の潜在ニーズを顕在化する

香川さんは営業という分野で大きな成功を収められている営業パーソンのお一人だと思いますが、ご自身ではその成功を実現できた秘訣は何だとお考えですか?
特にお客様との関係構築についてお教えいただけますか?

『潜在ニーズの顕在化』が本当に重要だと思っています。お客様自身も気づいていないことを、質問によって引き出していきます。『なるほど、香川さんのおかげで大切なことに気づきました!』と言われることがありますが、実は私は質問をしただけなんです。

そのプロセスを具体的に教えていただけますか?

例えば『今の仕事の延長線上で、こんなことに興味はありませんか?』と質問すると、お客様は『確かにそうですね…』と気づいていただき、新しい一歩を踏み出すきっかけになります。このように共感を得てから関係が始まるんです。ただ、私もこのスキルは最初から持っていたわけではありませんでした。

私も営業をしていた頃は同じような経験をしました。
最初は成果が上がらない時期に『どのような方でもいいのでお客様にしたい』と考えていましたが、ある程度実績が出てくると『自分が本当に大切にしたいお客様とはどのような方だろう?』と考えるようになりました。

まさにその通りですね。自分が興味を持てるお客様だと、自然とその方のことを知りたくなり、会話もスムーズに進みます。何気ない対話の中から『あなたは話が面白いから』と言って商品を購入してくださるようになったりします。

人との良い繋がりは、商品やサービスを購入いただく決め手になることがありますよね。
特にこれからの時代はその傾向が強まると思っています。似たような商品は数多く存在するため、最終的には『人』で選ばれるようになります。
ちなみに、香川さんがお客様に対して大切にしている『スタンス』についてお聞かせいただけますでしょうか。

『真実の自分』で接することが大切だと考えています。先輩や上司、もちろんお客様にも配慮しますが、本心で伝えることを意識しています。『このような考え方、素晴らしいですね!』と素直に伝えるなど、自分の心を率直に表現するようになってきたのだと思います。

嘘で塗り固めていると、どこかで自分を欺くことになってしまいますしね・・・
そして他者からもどこかで欺かれることになりますよね。
真実の自分と向き合うことが本当に大切なんだと感じました。

でも、時には寂しい経験をすることもあります。最近の出来事ですが、10年間お世話になったゴルフのコーチとの関係について悩むことがありました。納得がいかないことがあり、率直に思いを伝えたところ、関係が途絶えてしまったのです。しかし、それも一つの選択として受け入れられるようになりました。

そうですね、無理をした自分で繋がっていた関係だったのかもしれません。
真実の思いを相手が受け入れられなかったということは、香川さんのステージがさらに高いレベルへと進まれたということなんだと思います。

そう考えるようにしています。寂しい気持ちはありますが、途切れていくご縁があれば新たな出会いも生まれるものです。実際、その後に日報コンサルタントの中司さんとの出会いがありました。毎日の振り返りを日報として記録し、それに対してコメントをいただきながら、本当に取り組みたいことを見出していく支援をしてくださる方です。

『本当はどうしたいのか』という自分自身への問いかけは、非常に重要なことですね。
カウンセラーとしても実感しますし、営業担当者としても相手の潜在ニーズを把握するために欠かせない視点です。

私もお客様に『本当はどうしたいのですか?』とお聞きすることがあります。それは、真に相手の意図が伝わってこないときです。表面的な会話に留まっていると感じた際に、本音を引き出すためにこのような質問をしています。

私もクライアントにカウンセリングをするとき、似たようなアプローチをしています。直接聞くこともありますが、質問されることに慣れていない人もいるので、外側から柔らかく層を剥がしていくような感覚で確認していきます。

ちなみに、大崎さんはどうやって本音を見抜くのですか?

まず「違和感」として感じることが多いですね。あとは言っていることがちぐはぐになってくる、言っていることと行動が全く異なるという点から見ていきます。

言っていることと行動が違う人、確かに多いですよね・・・

これはやむを得ないことなんです。トラウマが原因なんですよね。
今まで本当の自分を受け入れてもらえなかった経験から、本心を隠してしまう。
特に家庭環境が厳しかったり、逆に甘やかされすぎて親の愛に応えなければならないと思っていたりする人に多いですね。

若手と先輩をつなぐ「通訳者」としての使命

最後に、営業に課題を抱える経営者の方々へのメッセージをお願いできますか?

本質的なことは、その人が思っている本心や心の底にあるものをしっかりと聴き取ることだと思います。社長の前で社員は本音を言えないかもしれませんが、それを知らないと会社はおかしくなってしまいます。営業の現場でも同じで、お客様の本当のニーズを引き出せなければ、真の問題解決はできません。

その視点はとても重要ですね。
ただ、実際に組織内の本音はどのように引き出せばよいでしょうか?

例えば第三者を介して聞き取りをするとか、匿名でのフィードバックシステムを作るとか、工夫が必要だと思います。私がプルデンシャルで課題と感じているのは、世代間の認識の違いです。長年会社に貢献されてきたベテラン社員の方々と若手社員との間で、コミュニケーションに隔たりがあるように感じているんです。「彼らは私たちとは考え方が異なる」「時代背景が違う」という理由でコミュニケーションが限られてしまうことがあります。しかし私から見ると、素晴らしい能力を持った若手人材が入社しても、残念ながら退職してしまうケースがあるのです。これは互いの本音を理解し合えていない、真摯に向き合えていないからではないかと思っています。

これは多くの会社が抱える課題と共通していますね。
ベテラン社員と若手社員がうまく調和していくためには何が必要でしょうか?

簡単に解決できるような課題ではないですよね。ただ、2025年4月からある公益団体のプルデンシャル会長を任されることになったので、若い人材にフォーカスした取り組みをたくさんやっていきたいと考えています。若手が活躍できる会社になれば、会社全体が繁栄するはずです。世の中の経営者の方々にも言えることですが、若手の成功事例を増やすことで組織全体が間違いなく変わっていきます。トップダウンで変えようとするより、成功事例を積み上げていく方が自然な変化につながるのです。昇竜のように仲間と共に昇っていくイメージです。

具体的にはどのような取り組みを考えていますか?

若手が主体となる研修会や、成功事例の共有会などを企画しています。また、世代間の「通訳者」としての役割も担っていきたいと思います。上の世代も会社を大切に思い、存続させたいという強い願いを持っていますが、どのように行動すべきか模索している状況です。その思いを若手に伝え、逆に若手の考え方や価値観を上の世代に伝える架け橋になることが大切だと思っています。

橋渡し役の存在はとても重要ですね!経営者自身がその役割を果たすこともできるでしょう。
ここまで香川さんの経験を惜しみなくお聞かせいただき、ありがとうございました。
香川さんのような「真実の自分」で向き合える方がいらっしゃることで、会社も、そしてお客様も幸せになれるのだと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました!

ギャラリー








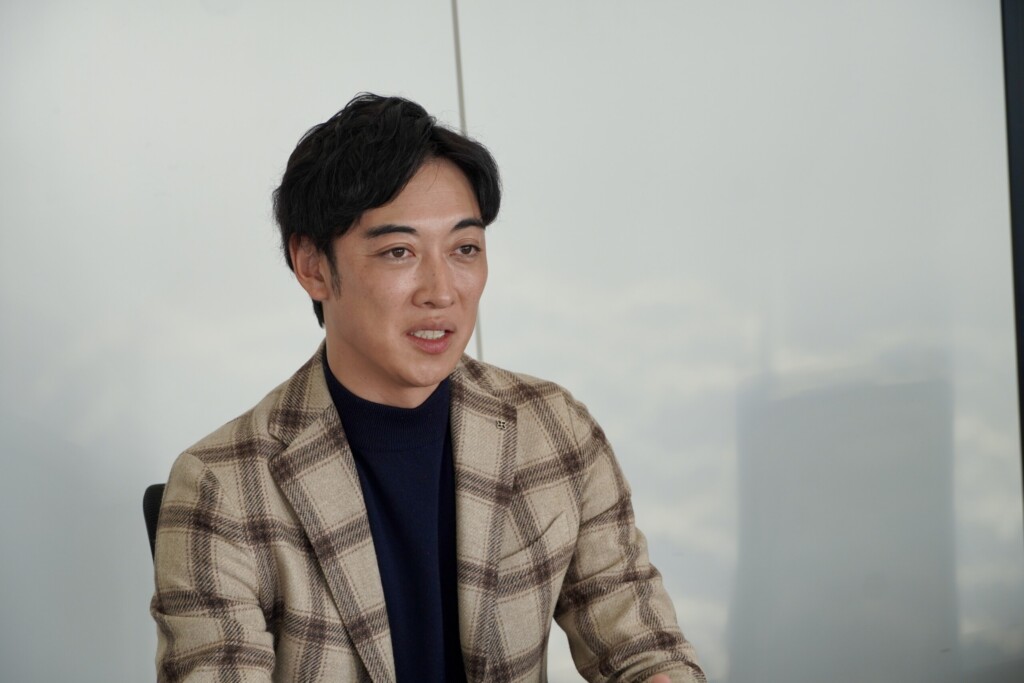
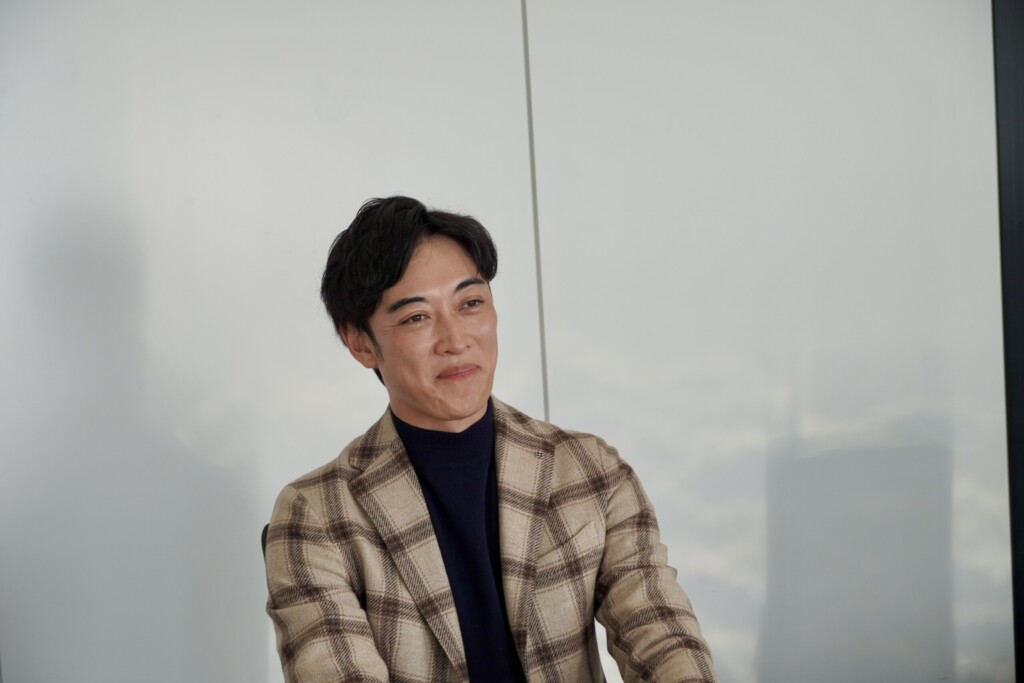

プロフィール

プルデンシャル生命保険株式会社
エグゼクティブライフプランナー
香川 壽宗
Toshimune Kagawa
不動産業界を経て2009年1月にプルデンシャル生命保険株式会社に入社。セールスの技術を磨き、マーケットを開拓しMDRT(Million Dollar Round Table)を13年連続で達成。
終身会員の資格を取得し、COT(Court of the Table)を7回、TOT(Top of the Table)を2回達成。また、438週連続での挙績を記録。「私が選ぶMy担当ライフプランナー」を11回受賞し、支社コアバリュー賞も7回受賞。
現場で培ったノウハウを体系化し、多くのライフプランナーに伝授。その後、独自のセールスプロセスを確立し、保険営業チーム「侍」を設立。チームにはCOT達成者3名、MDRT達成者40名以上が在籍している。
インタビュアープロフィール

株式会社Realize
代表取締役
大崎 美紀
愛知県出身の心理カウンセラー。ITベンチャー企業での営業を経て、アメリカン・エキスプレスでは富裕層向け飲食店サービスを担当。その後、金融ベンチャーで富裕層向けマーケティングに携わる。産後の心の変化をきっかけに心理学を学び始め、2021年に株式会社Realizeを設立。
現在は経営者を中心に心理カウンセリングや講座を提供し、紹介を中心に事業を展開。座右の銘は「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから」「日日是好日」。趣味はワイン、ゴルフ、インテリア。
2025年8月にはタイへの移住を予定しており、国内外での活動を通じて経営者の心の状態を整え、より良い企業へと発展するサポートを目指している。
「6割できればいい」と割り切れる組織を作った
あなたの経験を、次の経営者へ届けませんか?
若手育成のノウハウを体系化し、チーム全体の営業力を底上げしてきた経営者の皆様。その取り組みや想いをコントリが運営するセールスカレッジのインタビュー記事として発信しませんか?100名以上のCEOインタビュー掲載実績を持つメディアで、あなたの育成哲学が同じ課題を抱える経営者の道標になります。


