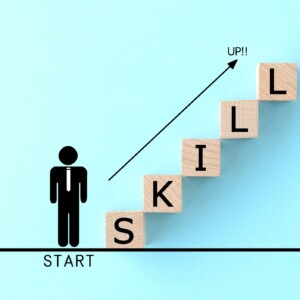営業戦略とは?経営者のための実践的な立て方とフレームワーク解説
「このままでは会社の成長が止まってしまう…」
そんな危機感を抱えている経営者の方は少なくないでしょう。特に、営業活動が属人的で、組織的な成果につながっていないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。実は、この課題は適切な営業戦略を立てることで解決できます。なぜなら、営業戦略は「やみくもな営業活動」を「計画的で効率的な営業活動」に変えるための羅針盤となるからです。
この記事では、中小企業の経営者の方でも実践できる、具体的な営業戦略の立て方からフレームワークの活用法まで、わかりやすく解説していきます。
効果的な営業戦略の立て方と実践ステップ
属人的な営業活動から組織的な営業活動への転換を図りたい。新規顧客の開拓を効率的に進めたい。売上を安定的に伸ばしていきたい。こうした課題を抱える企業にとって、営業戦略の立案と実行は避けて通れません。ただし、経営資源に限りがある中で、どのように戦略を立て、実行していけばよいのか悩むことも多いでしょう。
ここでは、現場での実践を重視しながら、準備から評価まで、営業戦略に関する具体的なステップを解説していきます。戦略の立て方を理解し、実践することで、効率的な営業活動の実現と売上の向上を目指しましょう。

営業戦略の定義と活用シーン
営業戦略とは、企業の営業目標やミッションを達成するための指針であり、市場環境や自社の強み、経営資源を踏まえた上で、「どのような顧客に」「どのような価値を」「どのように提供するか」を明確にした中長期的な計画です。
営業戦略は、企業の状況に応じて様々な場面で活用できます。例えば、新規市場への参入を検討する際の指針として、既存市場でのシェア拡大を目指す際の方向性として、また、営業部門の生産性向上を図る際の基準として機能します。
重要なのは、戦略を立てること自体が目的ではないということです。営業戦略は、限られた経営資源を最適に配分し、効率的に成果を上げるための道具として活用することが大切です。

戦略立案前の準備と必要な要素
効果的な営業戦略を立案するためには、まず現状を正確に把握することが不可欠です。具体的には、市場環境、顧客ニーズ、競合状況、自社の強みと弱み、そして現在の営業活動に関するデータの収集と分析が必要となります。この分析には3C分析、SWOT分析、ランチェスター戦略、ファイブフォース分析、パレートの法則などのフレームワークを活用することが重要です。
市場環境の分析では、市場規模やトレンド、規制環境などの外部要因を確認します。顧客ニーズの把握では、既存顧客へのヒアリングや市場調査を通じて、真の課題や購買決定要因を理解することが重要です。
競合分析では、主要な競合企業の強みや弱み、市場でのポジショニング、営業アプローチなどを整理します。自社分析では、商品・サービスの特徴、営業リソース、過去の成功事例や失敗事例などを客観的に評価します。
これらの情報を収集・分析する際は、できるだけ具体的なデータに基づいて行うことが重要です。「なんとなく」や「気となる」といった感覚的な判断は避け、数値やファクトに基づいた分析を心がけましょう。
営業戦略の立案プロセス
営業戦略の立案は、目標設定から始まります。目標は、経営目標と整合性のとれた具体的な数値目標として設定します。「売上を増やす」といった漠然とした目標ではなく、期間や数値を明確にした目標を立てることが重要です。
目標設定の次は、ターゲット市場とターゲット顧客の選定です。自社の強みが最も活きる市場セグメントはどこか、最も効率的にアプローチできる顧客層はどこかを検討します。このとき、市場の魅力度(市場規模、成長性、競争環境など)と自社の競争力(商品力、営業力、ブランド力など)の両面から評価することが大切です。
ターゲットが決まったら、具体的な営業アプローチを検討します。商品・サービスの価値提案、価格戦略、営業チャネル、プロモーション方法など、具体的な施策を検討していきます。この際、経営資源の制約を考慮し、実行可能な施策を選択することが重要です。
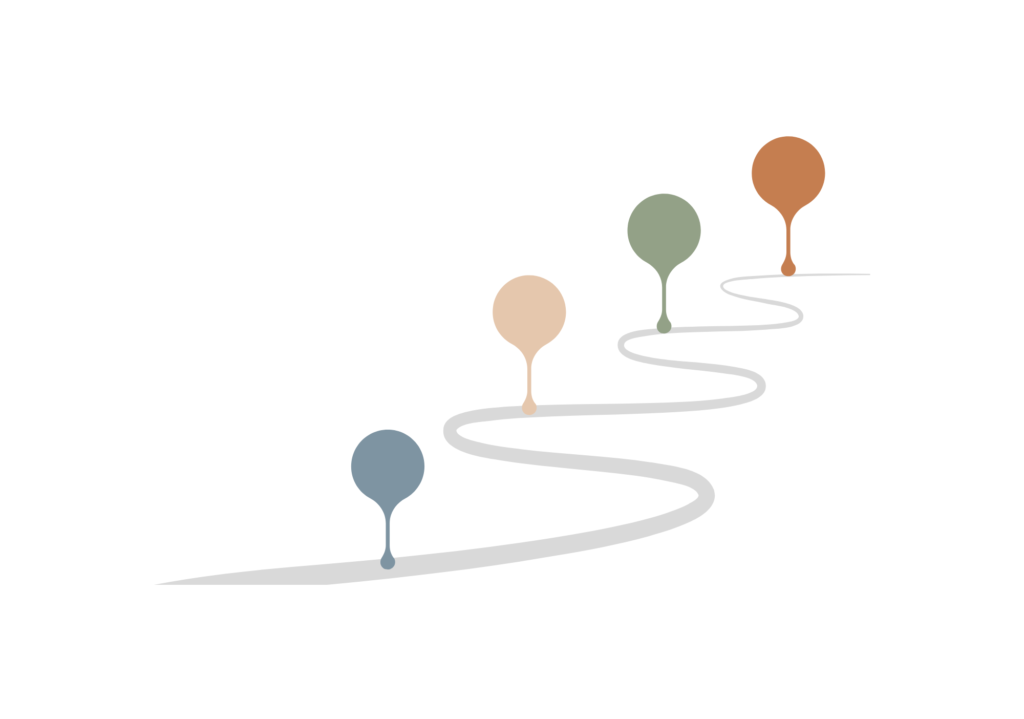
戦略を実行計画に落とし込む方法
立案した戦略を実行に移すためには、具体的な行動計画への落とし込みが必要です。まず、戦略目標を達成するために必要な具体的なアクションを洗い出します。例えば、「新規顧客開拓」という戦略であれば、見込み客リストの作成、アプローチ方法の確立、商談プロセスの設計などが必要となります。
次に、それぞれのアクションについて、担当者、実施時期、必要なリソース、期待される成果を明確にします。この際、現場の営業担当者の意見も積極的に取り入れ、実行可能性の高い計画を作ることが重要です。
計画は、全体のスケジュールとマイルストーンを設定し、進捗管理がしやすい形にまとめます。また、計画の実行に必要なツールや仕組みの整備も忘れずに行いましょう。例えば、顧客管理システム(CRM)や営業支援ツール(SFA)の導入を検討することも有効です。
戦略の評価と改善サイクルの作り方
営業戦略の成否を判断し、継続的な改善を図るためには、適切な評価指標(KPI)の設定と管理が不可欠です。KPIは、最終的な成果指標(売上高、利益率など)だけでなく、プロセス指標(商談件数、提案件数、成約率など)も設定することが重要です。
KPIの測定と評価は定期的に行い、目標との乖離がある場合は、その原因を分析し、必要な改善策を講じます。評価・改善のサイクルは、月次や四半期など、適切な期間を設定して実施します。
また、市場環境の変化や競合動向なども定期的にモニタリングし、必要に応じて戦略自体の見直しも検討します。戦略の評価と改善は、経営層だけでなく、現場の営業担当者も参加して行うことで、より実効性の高い改善につながります。
営業戦略を成功に導くフレームワーク活用法
営業戦略の立案において、フレームワーク(分析の枠組み)の活用は非常に効果的です。適切なフレームワークを用いることで、市場環境や自社の状況を体系的に分析し、効果的な戦略を導き出すことが可能となります。しかし、「フレームワークは理論的すぎて実務に活かせない」「どのフレームワークを使えばよいかわからない」といった声も少なくありません。
ここでは、実務で使いやすい基本的なフレームワークについて、具体的な活用方法を解説していきます。これらのフレームワークを適切に活用することで、より効果的な営業戦略の立案が可能となるでしょう。
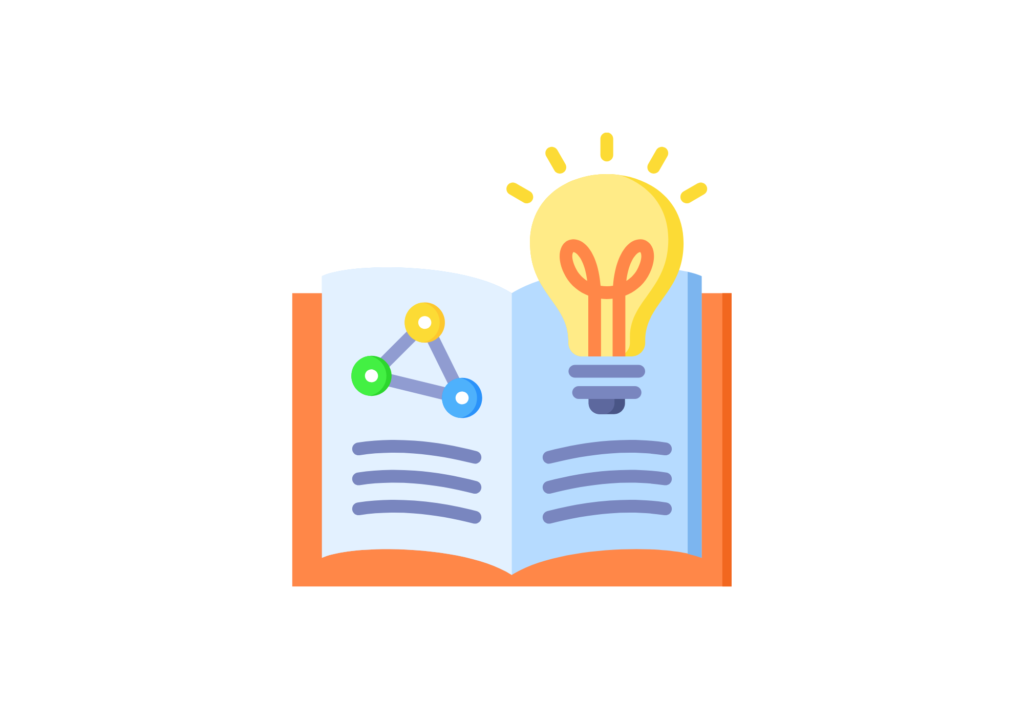
市場環境を把握する3C分析
3C分析は、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から事業環境を分析するフレームワークです。この分析を通じて、自社を取り巻く環境を総合的に理解し、効果的な戦略立案につなげることができます。
まず、Customer(顧客)の分析では、顧客が抱える課題や潜在的なニーズ、購買行動の特徴などを明らかにします。具体的には、以下のような観点で分析を行います。
| 分析項目 | 具体的な観点 |
|---|---|
| 顧客の課題 | 業務上の課題、経営上の課題、現状の不満点 |
| 購買決定要因 | 価格、品質、納期、サービス内容、信頼性 |
| 購買プロセス | 情報収集方法、意思決定者、決定までの期間 |
次に、Competitor(競合)の分析では、主要な競合企業の特徴や強み、市場でのポジショニングなどを整理します。商品・サービスの特徴だけでなく、営業手法や価格戦略なども含めて分析することが重要です。
最後に、Company(自社)の分析では、自社の強みや弱み、経営資源の状況などを客観的に評価します。特に、競合と比較した際の差別化ポイントを明確にすることが、戦略立案において重要となります。
3C分析の基本的な概要をご紹介しましたが、実際の分析作業ではもっと詳細な手順とノウハウが必要です。「どの情報をどうやって集めるべきか」「分析の精度を高めるコツは何か」など、現場で直面する具体的な課題に対する解決策を、実践的なテンプレートと共に詳しく解説した記事をご用意しています。ぜひご覧ください。
>> 3C分析のやり方完全ガイド|実践テンプレートで確実に進める方法
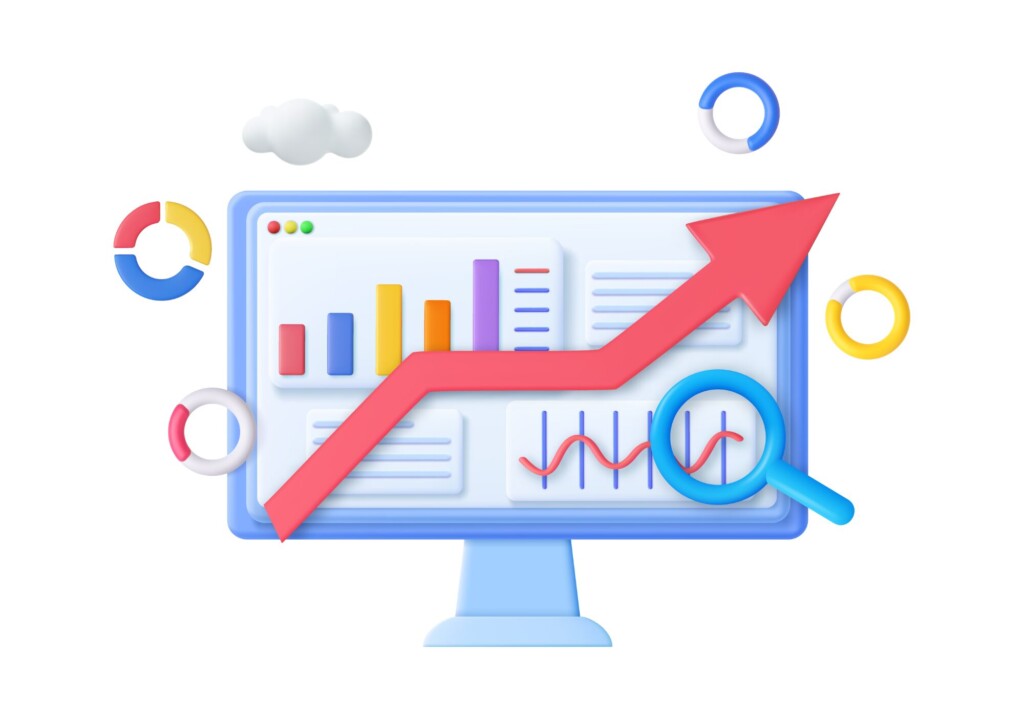
自社の強みを活かすSWOT分析
SWOT分析は、内部要因である「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」、そして外部要因である「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つを分析するフレームワークです。この分析を通じて、自社の強みを活かし、弱みを補完する戦略を導き出すことができます。
分析の手順としては、まず内部環境である強みと弱みを洗い出します。営業力、商品力、技術力、ブランド力など、様々な観点から自社の特徴を整理します。この際、競合との比較や顧客からの評価なども参考にしながら、客観的な分析を心がけましょう。
次に、外部環境である機会と脅威を分析します。市場トレンド、技術革新、規制変更、競合動向など、自社を取り巻く環境変化を幅広く検討します。特に、今後の事業展開に影響を与える可能性のある要因を見落とさないよう注意が必要です。
これらの分析結果をもとに、以下のような戦略オプションを検討していきます。
- 強み×機会:強みを活かして市場機会を捉える戦略
- 強み×脅威:強みを活かして脅威に対抗する戦略
- 弱み×機会:弱みを克服して機会を活かす戦略
- 弱み×脅威:弱みを補強して脅威の影響を最小化する戦略
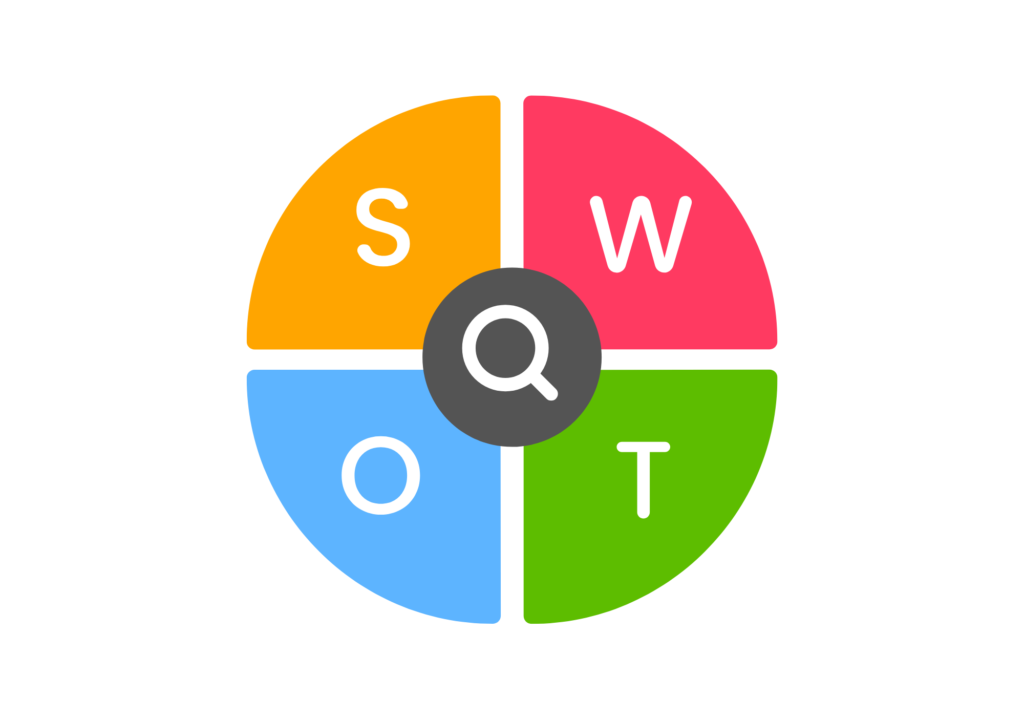
SWOT分析の基本的な枠組みと4つの戦略オプションについてご理解いただけましたでしょうか。では次は、この知識を実際のビジネスで活用し、具体的な売上アップにつなげていく段階です。分析の準備から戦略立案まで、現場ですぐに実践できる具体的な手順を、初心者にもわかりやすく解説した記事をご用意しています。ぜひご覧ください。
>> 初めてのSWOT分析!売上アップにつながる戦略立案の具体的手順
営業施策を具体化する4P分析
4P分析は「Product(商品・サービス)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(プロモーション方法)」の4つを分析し、どのように販売すべきか具体的な営業戦略を立案するためのフレームワークです。この分析を通じて、戦略を実行可能な施策レベルまで具体化することができます。
Product(製品)の分析では、商品・サービスの特徴や競争優位性を明確にします。単なる機能や性能だけでなく、顧客にとっての価値や解決できる課題という観点から整理することが重要です。
Price(価格)の分析では、価格戦略や収益モデルを検討します。市場価格や競合状況を踏まえながら、適切な価格帯や価格体系を設定します。また、値引き基準や支払条件なども含めて検討が必要です。
Place(流通)の分析では、商品・サービスの提供方法や販売チャネルを検討します。直接販売やパートナー経由の販売など、最適な販売チャネルの組み合わせを考えます。
Promotion(プロモーション)の分析では、顧客とのコミュニケーション方法を検討します。営業活動やマーケティング施策を通じて、どのように顧客にアプローチしていくかを具体化します。
これらの要素は相互に関連しているため, 全体のバランスを考慮しながら検討を進めることが重要です。

フレームワークの使い分けと選択基準
フレームワークは、それぞれ特徴や得意分野が異なります。効果的に活用するためには、分析の目的や状況に応じて適切なフレームワークを選択することが重要です。
3C分析は、市場環境を包括的に理解し、自社のポジショニングを検討する際に効果的です。新規市場への参入検討や、既存市場での戦略見直しなど、基本的な市場分析が必要な場面で活用します。
SWOT分析は、自社の現状を客観的に評価し、今後の方向性を検討する際に有用です。特に、中期的な戦略立案や、重点施策の検討などの場面で効果を発揮します。
4P分析は、具体的な営業施策を検討する際に活用します。戦略を実行計画に落とし込む段階で、実務的な視点から施策を具体化する際に役立ちます。
これらのフレームワークは、単独で使うだけでなく、組み合わせて使用することも効果的です。例えば、3C分析で市場環境を把握し、SWOT分析で戦略の方向性を定め、4P分析で具体的な施策を検討するといった流れです。
重要なのは、フレームワークを使うこと自体が目的化しないことです。フレームワークはあくまでも思考を整理するための道具であり、実務での活用を念頭に置いた柔軟な使い方が求められます。
営業戦略と営業現場の効果的な連携方法
優れた営業戦略も、現場で適切に実行されなければ成果には結びつきません。多くの企業が直面するのが、戦略と現場の乖離という課題です。「戦略は立てたものの、なかなか現場に浸透しない」「営業担当者がバラバラな動きをしている」「属人的な営業から抜け出せない」といった悩みを抱えていないでしょうか。
ここでは、営業戦略を現場で効果的に実行するための具体的な方法と、発生しがちな課題への対処法を解説していきます。戦略と現場をつなぐ実践的なアプローチを理解し、組織全体で成果を上げる営業体制の構築を目指しましょう。

営業戦略と営業戦術の違いを理解する
営業戦略と営業戦術は、しばしば混同されがちですが、その性質と役割は大きく異なります。営業戦略は営業目標を達成するための「計画」であり、市場選択や価値提案の方向性を示すものです。一方、営業戦術は営業戦略を実現するための具体的な「手段」を指します。
両者の違いを理解するため、以下の表で整理してみましょう。
| 項目 | 営業戦略 | 営業戦術 |
|---|---|---|
| 時間軸 | 長期的な視野 | 短期から中期的 |
| 範囲 | 組織全体の方向性 | 個別の活動計画 |
| 内容 | 目標設定、市場選択、資源配分 | 具体的な営業手法、アプローチ方法 |
| 決定者 | 経営層、営業部門責任者 | 現場マネージャー、営業担当者 |
戦略と戦術は、車の運転に例えるとわかりやすいでしょう。目的地(目標)を決め、そこまでのルート(戦略)を設定するのが戦略的な思考です。一方、実際の運転操作や交通状況への対応(戦術)は、状況に応じた具体的な行動となります。
重要なのは、戦略と戦術の一貫性です。戦術は戦略に基づいて立案され、戦略は適切な戦術によって実現されます。この関係性を理解することで、より効果的な営業活動が可能となるのです。
営業部門への戦略共有と浸透施策
営業戦略を効果的に実行するためには、まず営業部門全体で戦略を正しく理解し、共有することが不可欠です。ここでは、戦略の共有と浸透のための具体的な施策について説明します。
まず重要なのは、戦略の「見える化」です。複雑な戦略を、誰もが理解できる形で表現することが必要です。具体的には、目標、ターゲット顧客、提供価値、アプローチ方法などを、1枚のシートにまとめると効果的です。視覚的な資料を用いることで、戦略の全体像を把握しやすくなります。
次に、戦略の背景や意図を丁寧に説明することが大切です。なぜこの戦略が必要なのか、どのような成果が期待できるのか、現場の営業活動にどう影響するのかなど、営業担当者の疑問に答える形で説明を行います。
定期的なフォローアップも欠かせません。月次や四半期での進捗確認ミーティング、成功事例の共有会、課題解決のためのワークショップなど、様々な機会を通じて戦略の浸透を図ります。
営業活動の仕組み化と標準化
属人的な営業から組織的な営業への転換を図るためには、営業活動の仕組み化と標準化が重要です。ここでは、効果的な仕組み化と標準化のアプローチについて解説します。
まず、営業プロセスの標準化から始めます。見込み客の発掘から商談、成約に至るまでの基本的な流れを整理し、各段階で必要な活動や判断基準を明確にします。この際、ベストプラクティスを参考にしながら、自社に適した形でプロセスを設計することが重要です。
次に、営業活動の「型」を作ります。商談の進め方、提案資料の作成方法、見積もりの提示方法など、基本的な営業活動の手順やポイントを整理します。ただし、過度な標準化は営業担当者の創意工夫を阻害する可能性があるため、バランスを考慮することが大切です。
さらに、成果を上げている営業担当者のノウハウを組織的に共有する仕組みも必要です。定期的な事例共有会や、ナレッジデータベースの構築などを通じて、個人の知見を組織の資産として蓄積していきます。

組織的な営業体制の構築方法
効果的な営業体制を構築するためには、人材の適切な配置と役割分担が重要です。ここでは、少人数でも機能する営業体制の作り方について説明します。
まず、営業機能の分業化を検討します。従来型の「営業担当者が全てを担当する」モデルから、機能別の分業制へと移行することで、効率化と専門性の向上を図ります。例えば、見込み客の開拓、商談、契約管理などの機能を分けることで、それぞれの業務に集中できる環境を作ります。
次に、営業支援体制の整備です。営業担当者が本来の営業活動に集中できるよう、提案資料の作成や見積書の準備、契約書の作成など、営業支援業務を効率化する仕組みを整えます。デジタルツール(SFAやCRM)の活用も、業務効率化の重要な要素となります。
さらに、チーム制の導入も検討に値します。個人プレーではなく、チームとして成果を上げる体制を作ることで、ノウハウの共有や相互支援が促進されます。また、新人の育成もチーム単位で行うことで、より効果的な人材育成が可能となります。
営業戦略の運用と継続的な改善
営業戦略を立案しても、それを効果的に運用し、継続的に改善していくことは容易ではありません。特に、日々の営業活動に追われる中で、戦略の実行状況を把握し、必要な修正を加えていくことは大きな課題となっています。しかし、適切なデータ収集と分析、効率的なツールの活用、そして定期的な見直しと改善のサイクルを確立することで、より効果的な営業戦略の運用が可能となります。
ここでは、営業戦略を成功に導くための具体的な運用方法と、継続的な改善のための実践的なアプローチを解説していきます。

営業データの収集と分析の基本
営業活動の改善には、適切なデータの収集と分析が不可欠です。しかし、「どのようなデータを集めればよいのか」「集めたデータをどう活用すればよいのか」と悩む声も少なくありません。まずは、基本的なデータ収集と分析の方法から始めていきましょう。
収集すべき基本的な営業データには、以下のようなものがあります。これらのデータは、営業活動の効果測定と改善に直接関係する重要な指標となります。
| データ項目 | 収集のポイント | 活用方法 |
|---|---|---|
| 商談件数 | 新規・既存の区分、商談段階の記録 | 営業活動量の把握、ボトルネックの特定 |
| 成約率 | 商談段階ごとの推移、商品別の傾向 | 営業プロセスの改善、重点商品の選定 |
| 顧客接点データ | 訪問・電話・メールなどの履歴 | 顧客との関係性強化、最適なアプローチ方法の特定 |
データ収集は、売上や商談件数など重要業績評価指標(KPI)に直結する項目から開始することが効果的です。過度な収集項目は現場の業務効率を低下させ、データの正確性と品質の低下を招く可能性があります。
また、集めたデータは定期的に分析し、営業活動の改善につなげることが大切です。単なる数値の羅列ではなく、「なぜその結果になったのか」「どうすれば改善できるのか」という視点で分析を行います。

効率化のためのツール活用方法
営業活動の効率化には、適切なツールの活用が有効です。ただし、いきなり高度なツールを導入するのではなく、段階的な導入と活用を心がけることが重要です。ここでは、基本的なツールから順を追って説明していきます。
営業支援ツールを導入する際は、まずCRMシステムから始めるのが効果的です。顧客情報の一元管理や商談履歴の記録、進捗管理といった基本的な機能に絞ることで、現場への定着がスムーズになります。特に導入初期は、必要最小限の機能を備えたシンプルなツールを選択しましょう。高度な機能を最初から詰め込むと、かえって現場が混乱し、システムが使いこなせなくなる可能性があるためです。
次に、営業支援(SFA)ツールの導入を検討します。商談プロセスの管理、案件予測、活動報告の効率化など、より高度な機能を活用することで、営業活動の質を向上させることができます。
さらに、マーケティングオートメーション(MA)ツールの活用も視野に入れます。見込み客の育成、メール配信の自動化、リード獲得の効率化など、営業活動の幅を広げることが可能となります。
戦略の見直しと修正のタイミング
営業戦略は、市場環境の変化や自社の状況に応じて、適切なタイミングで見直しと修正を行う必要があります。しかし、「いつ」「どのように」見直すべきかの判断は容易ではありません。ここでは、戦略見直しの具体的な進め方について説明します。
営業戦略の見直しは、四半期ごとの実績評価と年次での包括的な分析を組み合わせて実施します。売上の停滞や市場環境の変化など、具体的な指標に基づいて見直しのタイミングを判断することが重要です。
さらに、以下のような状況が発生した場合は、臨時の見直しを検討する必要があります。
- 目標達成率が著しく低下している
- 市場環境に大きな変化が生じている
- 競合他社の動きに変化が見られる
- 自社の経営資源や体制に変更がある
見直しの際は、現状分析→課題特定→改善策立案→実行計画作成という流れで進めます。特に、現場からのフィードバックを重視し、実行可能性の高い改善策を導き出すことが重要です。

持続可能な営業の仕組みづくり
営業戦略を長期的に機能させるためには、持続可能な仕組みづくりが不可欠です。一時的な成果ではなく、継続的に成果を上げられる体制を構築することが重要です。
まず、PDCAサイクルの確立が基本となります。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のサイクルを、日次、週次、月次など、複数の時間軸で回していきます。各段階での役割と責任を明確にし、サイクルが途切れないようにすることが大切です。
次に、ナレッジマネジメントの仕組みを整備します。成功事例や失敗事例、有効な営業トークや提案手法など、営業活動で得られた知見を組織的に蓄積し、共有できる仕組みを作ります。デジタルツールを活用した情報共有プラットフォームの構築も有効です。
さらに、人材育成の仕組みも重要です。OJTと体系的な研修を組み合わせ、継続的なスキル向上を図ります。特に、データ分析やツール活用のスキルは、今後ますます重要性を増していくでしょう。
まとめ
長時間にわたりお読みいただき、ありがとうございます。営業戦略の立案と実行は、企業の成長に欠かせない重要な取り組みです。ここまでご紹介した内容を実践することで、属人的な営業から組織的な営業への転換を図り、持続的な成長を実現することができます。改めて、重要なポイントを整理してみましょう。
- 営業戦略は「やみくもな営業活動」を「計画的で効率的な営業活動」に変えるための羅針盤となり、限られた経営資源を最適に配分するための重要な指針となる
- 戦略立案には3C分析やSWOT分析などのフレームワークを活用し、市場環境や自社の状況を客観的に分析することが不可欠。ただし、フレームワークは思考を整理するための道具であり、使うこと自体が目的化してはいけない
- 現場への戦略浸透には「見える化」が重要。戦略の背景や意図を丁寧に説明し、定期的なフォローアップを通じて組織全体での理解と実践を促進する
- 持続的な成果を上げるには、適切なデータ収集と分析、効率的なツールの活用、そして定期的な見直しと改善のサイクルの確立が必要不可欠である
営業戦略は、一度立案して終わりではありません。市場環境の変化や自社の状況に応じて、継続的な改善を重ねていくことが重要です。この記事で解説した内容を参考に、自社の状況に合わせた効果的な営業戦略の立案と実行に取り組んでいただければ幸いです。